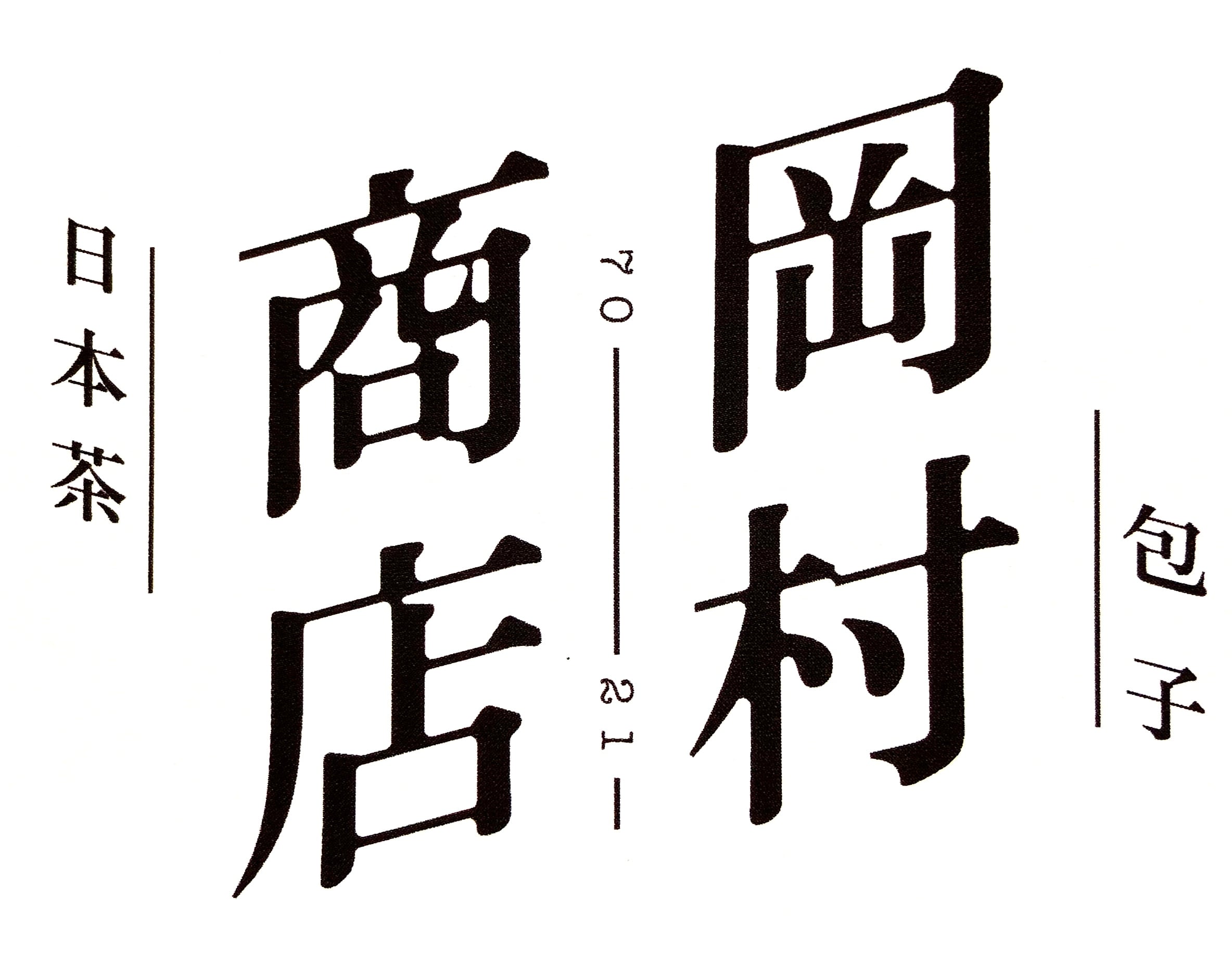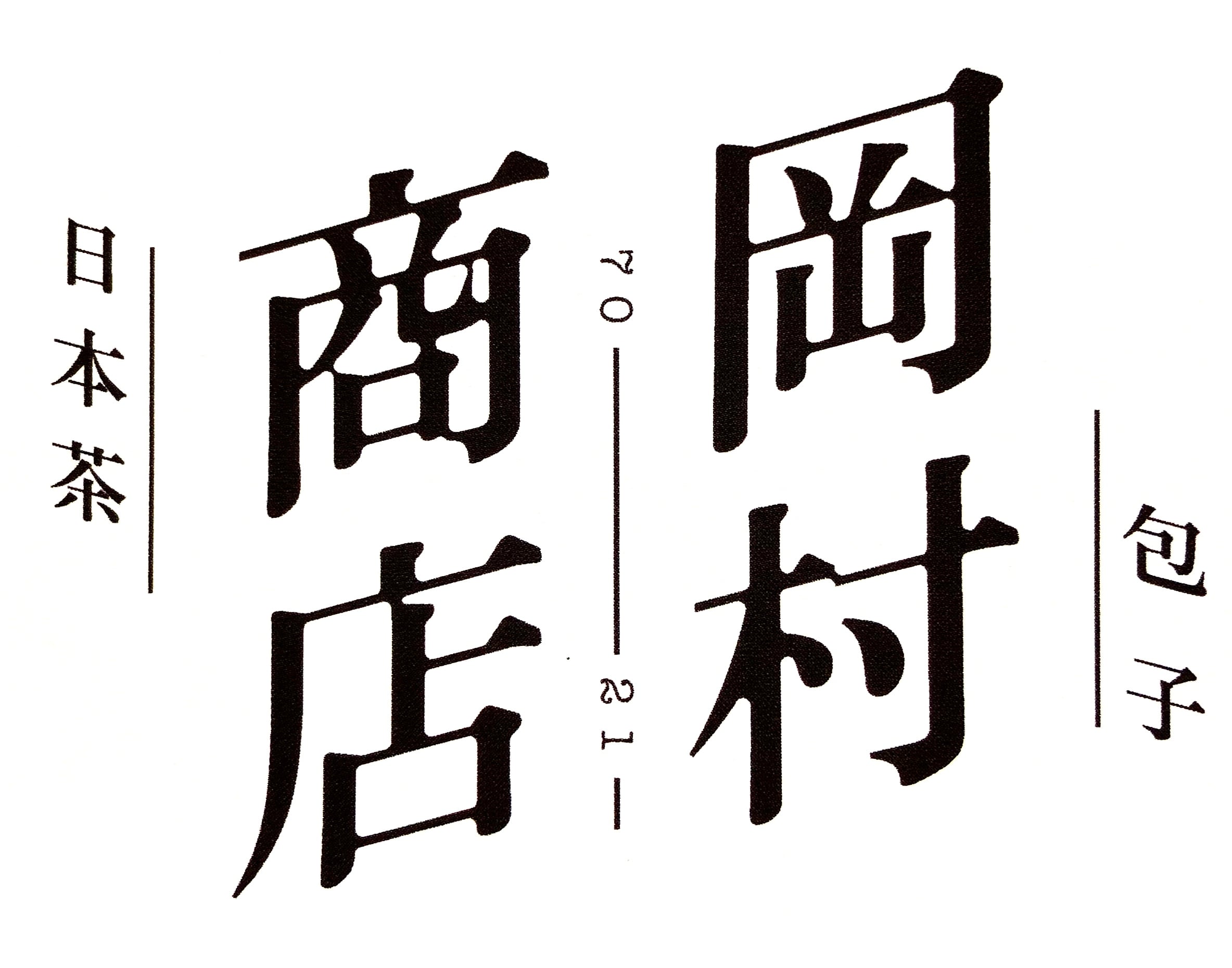2023/10/05 22:23
▶ この記事では...
ざっくりと日本茶の茶種を分類して皆様にご紹介いたします。
お茶選びの参考にご利用ください。

日本茶といえば、なにを思い浮かべますか?
緑色の飲み物というイメージが強いかもしれません。実際に私のスマートフォンでも「お茶」を変換すると、緑色のお茶が入った湯のみの絵文字が出てきます。しかし一口に緑茶とはいっても、さらに広げて日本茶全体を眺めると、そのバリエーションはとても豊かで、地方独特のものを加えるとまとめきれないほどの多用さを誇ります。
//
茶 / チャ / カメリア・シネンシス Camellia sinensis
お茶の樹を見たことがある方は、照りのある葉、花のふくらみ、実の成り方からしてツバキに似ているなと思ったかもしれません。実際にお茶の学名はカメリア・シネンシスといって、ツバキ科ツバキ属。ツバキのれっきとした親戚です。
なお、ゆず茶・黒豆茶・かわらけつめい茶など、実際にはチャを含まなくても「茶」と呼んでいる飲み物はたくさんありますね。このようなものを、まとめて茶外茶(ちゃがいちゃ)と指すこともあります。ところで「喫茶店でお茶しよっか」と言うとき、「茶」と2回も言っているのに本当に急須で淹れたりやかんで煮出したりしたお茶を飲みに行こうとしている人はほとんど居らず、おおむねコーヒーのことだと思われます。休憩や団らんのために飲むものの総称として「お茶」という表現が現代にも生きていることがわかります。
//
分類には様々な方法がありますが、当店では以下の7つに分けて考えています。
ただそれぞれが完全に分けられているわけではなく、いくつかの分類に同時にあてはまるお茶もありますので、ざっくりと全体像を眺めるためにご覧いただければ幸いです。
//
不発酵茶(緑茶) 酸化発酵 無〜弱
・蒸し製の茶
茶の酸化発酵を進めず、生葉を蒸してから揉み込みと乾燥を行う。
最も流通している。
煎茶 / 玉露 / かぶせ茶 / 蒸し製玉緑茶 / てん茶(→抹茶)
・釜炒り茶
茶の酸化発酵を進めず、生葉を釜炒りしてから揉み込みと乾燥を行う。
煎茶の登場以前には主流だったが、現在の生産量はとても少ない。
半発酵茶(烏龍茶)※当店では取り扱っていません
茶種によるが発酵程度を中程度進めてから釜炒りして製造する。
国内では一部を除いてほとんど生産されていない。
発酵茶(紅茶)
発酵程度が強い。蒸す・炒るなどの高温加熱工程がない。
国内では明治期に増産され、その後ほぼ消滅。近年急激に生産量が増えている。
後発酵茶
一部の地域にのみ残る。酵母やカビによる微生物発酵を経て生産されるお茶。
番茶(晩茶)
時期はずれの古い葉、摘み残した硬い葉、枝などを利用して作る。
地域によって製茶工程が全く異なり、「番茶で作った緑茶」「番茶で作った紅茶」などがある。
再加工茶
・焙じ茶
主に緑茶を高温焙煎して製造する
・ブレンド茶
玄米茶など、茶以外の原料とブレンドしたもの。
//
*補足「発酵」について
烏龍茶や紅茶の「発酵」
茶葉を揉み込むことで細胞が壊れ、茶葉に含まれる酸化酵素とカテキンが化学反応を起こすことをいう。色彩や香りに大きな変化が現れる。微生物は関与しておらず、一般に私達が「発酵食品」と呼ぶものとは仕組みが異なる。
後発酵茶の「発酵」
茶葉で酵母やカビを増殖させる。通常、「発酵食品」と私達が呼びならわしているのは、こちらのほう。